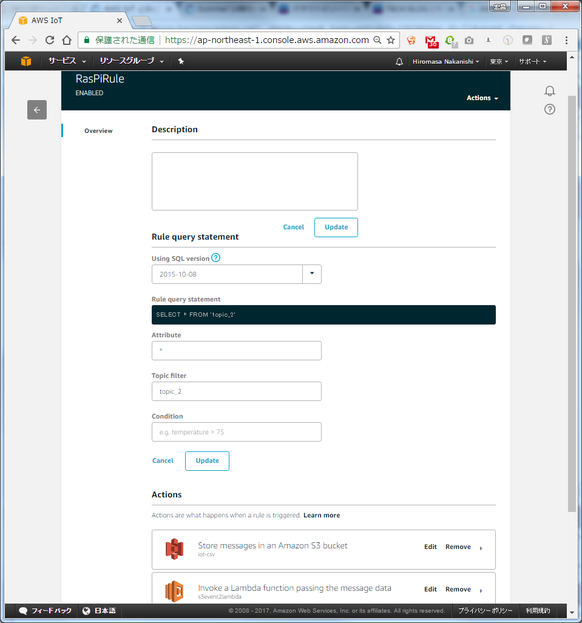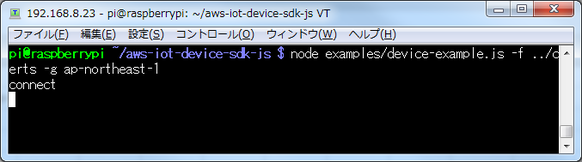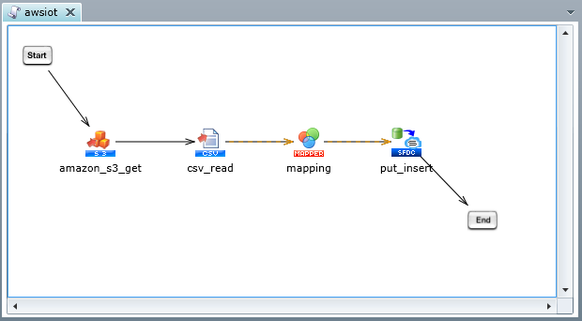はじめに
早いもので2017年も一ヶ月が過ぎようとしています。
寒い日が続きますね。
そんなときは家でRasberry Piで遊んじゃいましょう。
データフロー
今回試したRasberry Pi からのデータ連携フローは下記のようなイメージです。
- Rasberry Pi からMQTTでAWS IoTへデータをPublish
- AWS IoTでは受け取ったデータをS3へCSVで出力
- S3へ出力したことをLambdaからSkyOnDemandへHTTPリクエストを送信して通知
- SkyOnDemadのHTTPトリガでHTTPリクエストを受け取り、S3からCSVファイルをダウンロード
- ダウンロードしたCSVを展開しSalesforceへ書き込む
わざわざS3にCSVで保存しなくても、直接jsonでSkyOnDemadへ送れば。。。
という声が聞こえそうですが、ここはみんな大好きCSVを経由しました。
AWS IoT の設定
3ヶ月ぶり位にマネジメントコンソールからAWS IoTを触ったのですが、UIが全く別物になっていて、かなり右往左往しました。。。
AWS IoTの設定は基本的に下記の手順で行います。
- Thingの作成
- Pollicyの作成
- 証明書の作成
- 証明書をThingとPolicyに紐付ける
- Ruleの作成
- IAMロールの作成
マネジメントコンソール → AWS IoT → Connect → Configuring a device を使うと、上記1~4を順次実行できて便利です。
RuleでRasberry Pi から受け取ったMQTTデータを処理するフローを定義します。
ここでは、topic_2というトピック名で受け取り、S3へのPutとLambda関数の実行を定義しています。
Lambda Functionは下記のようにSkyOnDemandへHTTPリクエストを送信する簡単なものです。
なお、CID, SID, Authorization の各文字列はSkyOnDemandのHTTPトリガ作成時に作られるものです。
TECH BLOGで戸塚が詳しく書いてます。
var http = require ('https');
exports.handler = function(event, context) {
var options = {
hostname: 'www.skyondemand.net',
port: 443,
path: '/ws/trigger/awsLambda?cid=XXXXX&sid=XXXXX',
method: 'GET',
headers: {
'Authorization': 'Basic ' + 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
}
};
var req = http.request(options, function(res) {
res.setEncoding('utf8');
});
req.on('error', function(e) {
context.done('error', e);
});
req.write('data\n');
req.end();
};
Rasberry Pi からAWS IoTへPublishする環境の構築
Rasberry Pi側はAWSの「 IoT Device SDK for JavaScript 」を使います。
上記を使うためにはNode.jsをインストールする必要がありますが、かなり手順が多いです。
途中でエラー祭りが始まり四苦八苦した結果たどり着いた手順が下記です。
- nvmのインストール
$ git clone https://github.com/creationix/nvm.git ~/.nvm
$ source ~/.nvm/nvm.sh - node.jsのインストール
$ nvm install v6.9.4 - .bashrcへパスを通す
vi /home/pi/.bashrc
if [[ -f ~/.nvm/nvm.sh ]]; then
source ~/.nvm/nvm.sh
nvm use 6.9.4
fi - npmのインストール
$sudo apt-get install npm - expressのインストール
npm install express --save - aws-iot-device-sdk-js のインストール
ようやくここまで来ました!!
$ git clone https://github.com/aws/aws-iot-device-sdk-js.git
$ cd aws-iot-device-sdk-js
$ npm install mqtt
$ npm install blessed
$ npm install blessed-contrib
$ npm install minimist
$ npm install crypto-js
$ npm install websocket-stream
$ npm install date-utils - マネジメントコンソールで作成した証明書は下記に置いてあげます。
/home/pi/aws-iot-device-sdk-js/certs
さて、いよいよ実行です。
/home/pi/aws-iot-device-sdk-js/examplesにサンプルスクリプトが用意されてるので実行してみます。
ドキドキ!
$ node examples/device-example.js -f ../certs -g ap-northeast-1
お!connectって出来ますね。
S3にファイルは出来てるでしょうか?
できてますね!
中身は?
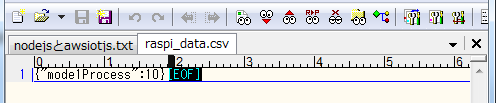
json形式で吐き出されてます。
CSV形式にしたいので、無理やり感はありますが、日時を付けてカンマで区切ってあげます。
修正したexample.js(一部)は下記です。
var dt = new Date();
var formatted = dt.toFormat("YYYY-MM-DD HH24:MI:SS");
if (args.testMode === 1) {
// device.publish('topic_2', JSON.stringify({
// mode1Process: count
// }));
device.publish('topic_2', '"'+formatted+'",'+'"'+count+'"');
} else {
device.publish('topic_1', JSON.stringify({
mode2Process: count
}));
}
S3に出力するファイルの拡張子も.csvに変更します。
変更は下記にて行います。
マネジメントコンソール → AWS IoT → Rules → Rule名 → Stone massage in an Amazon S3 buket
SkyOnDemandのHTTPトリガスクリプトの作成
AWS Lambdaから送信されたスクリプトはSkyOnDemandで受信し、下記手順を記述したスクリプトを起動します。
- S3バケットからCSVを取得する
- CSVファイルを読み込む
- SalesforceのカスタムオブジェクトへInsertする
イメージはこのようになります。
実際にRasberry Pi から送信してみます。
無事にSalesforceまでデータが到達しました!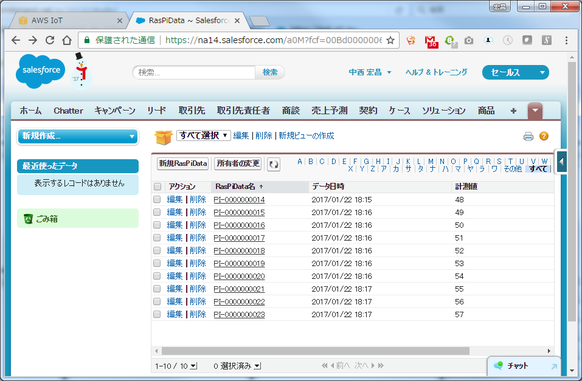
今回は最終的にSalesforceへデータを保存しましたが、SkyOnDemandならば様々なアダプタが用意されているので、他のクラウドやオンプレのDBなど保存先はいろいろ選択できます。
おわりに
今回の試行はRasberry Pi からデータが送られる度にSalesforceへデータをInsertしているので、SalesforceのAPIコール数をかなり消費します。
本来であれば、AWSのRDSやDynamoDBにデータを溜めて、集計、解析したものをSalesforceへ連携することを考えた方がよさそうです。
2017年1月22日にサービスインした「 DataSpider Cloud 」では、AWS DynamoDBアダプタが標準装備されたり、トリガ数の制限が無くなったりさらにIoT向けのサービスになっています。
同様に2017年3月に予定されているSkyOnDemandのアップデートでもAWS DynamoDBアダプタやAWS Kinesisトリガが追加され、益々IoTデータ連携機能が強化されます。
2016年はIoTがバズワードになりましたが、最近はAIという言葉のほうがよく聞きます。
AIはビッグデータを活用するアーキテクチャであり、IoTはビッグデータを集めるための「手段」です。
今回の試行のように、デバイスからクラウド、クラウドからクラウドというデータ連携ベースを一つ手の内に入れておくと今後応用が効きます。